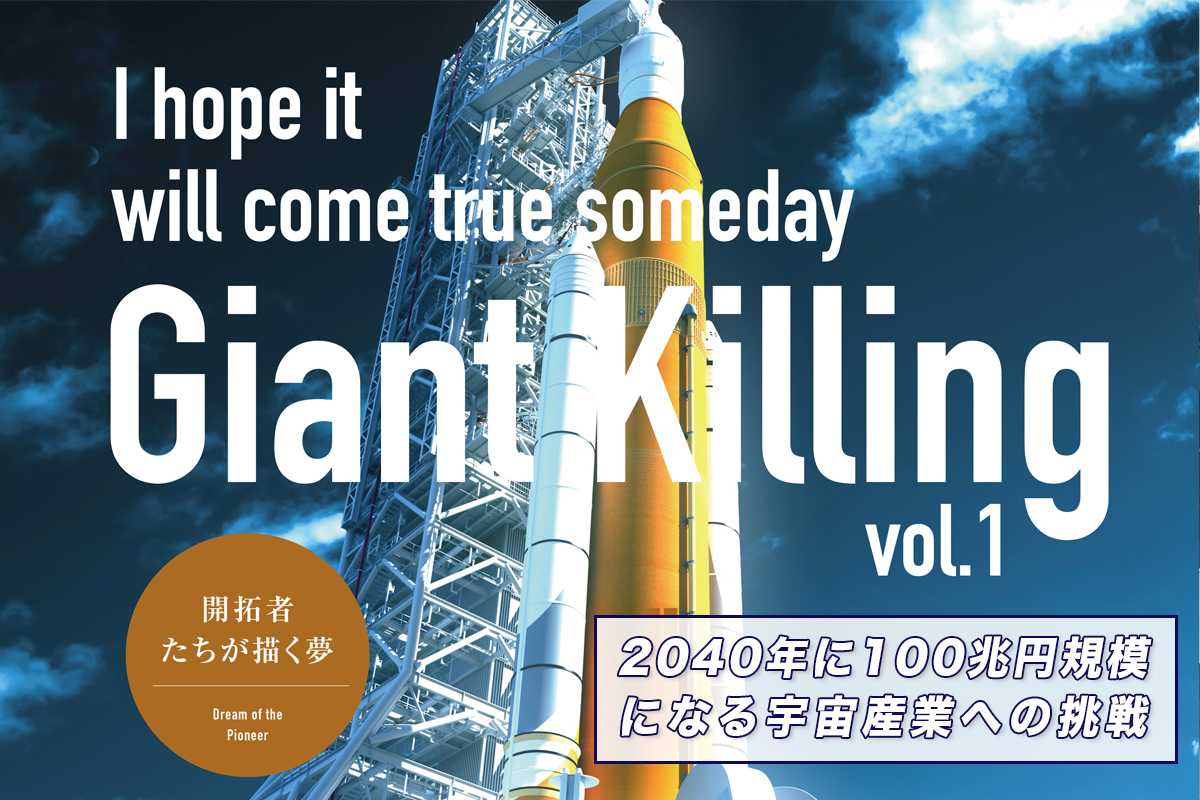
神奈川大学・宇宙ロケット部の高度100kmへの挑戦!国内第2位の記録を持つチームの挑戦と苦悩
宇宙に夢を持ち研究開発に取り組む
——神奈川大学宇宙ロケット部に入ろうと思ったきっかけは?
鈴木:高校時代に人工衛星と宇宙船の模型コンテストに出たことがきっかけです。模型製作で人工衛星や宇宙について学んでいくうちに、これからは航空宇宙について学びたいと考えるようになりました。
以前から航空宇宙分野に興味を持っていたのですが、そのなかでもロケットや航空機のエンジンに興味のあった自分は専門的に学ぶことができる研究室を探していました。YouTubeで高野研究室と宇宙ロケット部の燃焼試験動画を発見し視聴したところ強く感化されてしまい、高校時代から入部しようと決心していました。
和田:初めは友人の紹介で宇宙ロケット部を知りました。それまで「宇宙」は遠く難しい存在だと感じていましたが、広い宇宙に夢を持ち研究開発に取り組んでいる姿をみて、私もその一員として携わることができないかと感じました。
そこで興味を持ったのが「宇宙ビジネス」というジャンルです。入部時、文系の3年生だった私にとって、ハードウェアの面が目立つ宇宙産業にはとても追いつけず、ある意味それが宇宙事業における課題であるとも感じました。
そこで宇宙というキーワードを使った地上でのビジネスを展開し、面白さを発信していくことで、業界を盛り上げることができるのではないかと考えました。
目標は人工衛星や探査機を熱圏の入り口である低軌道に乗せる輸送手段になること
——ロケット部(研究室)の目標は高度100kmと聞きました。現在の課題は?
和田:大きくわけて、資金・場所・コミュニティの3つがあると考えています。JAXAさんなどが打ち上げている大型のロケットの開発には、多くの企業・団体が参画しており、それぞれ最新の技術や大規模な投資がなされています。
一方、私たち学生団体だけで開発を進めていくには、機体進化のための活動に資金的・場所的な限りがあります。そのため一層の産学連携が必要であると考えています。また、ハイブリッドロケットという技術を多くの人に知ってもらい、私たちの活動に興味を持ってもらう「発信力」も必要であると考えます。
私たちの活動や成果の発信はもちろん、今後興味を持っていただける方々へ夢を届けていくことが、宇宙に関わる学生としての1つの役割であると考えています。
鈴木:ロケット部と研究室の最終的な目標は高度100Kmを達成して、民間や個人で製作された人工衛星や探査機を熱圏の入り口である低軌道に乗せる輸送手段となることです。この目標を早期達成させるために、ロケット部と研究室の発足時にロードマップが設定されました。
現在の課題はこのロードマップ通りに到達高度を更新するということです。しかし、2021年の打ち上げ試験まではほとんどこのロードマップ通りに開発を進めることができていましたが、2022年の試験では到達高度が下がってしまいました。
ですが、燃焼試験の結果から到達高度が30Km近くなるだろうといわれていました。実際は、試験当日の天候が悪く強い風が観測されたので、本来定められていたロケットの落下範囲からはみ出てしまうことが予測されました。
そのためランチャーの打ち上げ角度を通常時から10度以上も下げて発射したことが原因となり到達高度を更新することができませんでした。 このような理由で、実際のロードマップから現在1年遅れてしまっている状況です。
どのように本来のロードマップに軌道を戻すかどうかがこれからの課題となってくると思います。
ハイブリッドロケットで高度100㎞を目指す

▶︎機体制作に使う機材や小型のロケットが並ぶ研究室
——神奈川大学宇宙ロケット部で扱っている「ハイブリッドロケット」の利点や、液体・固体ロケットとの違いは?
鈴木:私たちの製作しているハイブリッドロケットは急な衝撃などで爆発する危険性がなく安全です。また、あまり複雑な構造ではなく、ロケット本体の大きさが液体ロケットや固体ロケットに比べて小型であるため、取り扱いが前記のロケットに比べると大いに楽です。
さらに、ランチャーの組み立ては2日間あれば完了するのですぐに打ち上げることができます。これらが私たちの扱っているハイブリッドロケットの利点であると思います。
また、エンジンの燃焼方式が異なります。液体ロケットのエンジンは酸化剤と燃料のタンクがわかれていて、これらを燃焼室で混合させて自然着火もしくは点火させて燃焼させます。固体ロケットのエンジンはモーターケースが燃焼室を兼ねることで内側に固体燃料と酸化剤を混合させて固体化させたものを点火させる方式です。
私たちのハイブリッドロケットは、液体ロケットの酸化剤タンクと固体ロケットのモーターケースを合体させた仕組みであり、液体の酸化剤と固体の燃料を酸化剤タンクと直結させたモーターケース内で燃焼させるという仕組みです。
2040年100兆円規模になる市場にベットする
▶︎実際の打ち上げ試験の様子 固体燃料に着火し勢いよく噴射口がら炎が吹き出しロケットが打ち上がる瞬間
——NASAがロケット制作を民営化していったことからも、ロケット開発及び宇宙が身近になってきたと感じます。宇宙産業の未来をどのように捉えていますか?
和田:今後5年~10年で、さらに「日常生活」に身近な分野になってくると考えています。
というのも、一言「宇宙産業」といっても、ロケットや衛星、それらを使ったデータビジネスなど、幅広い市場への活用に可能性を秘めています。
また2040年には約100兆円規模の市場になるともいわれ、今後これらをエンタメや生活の一部として展開していくことで、さらなる市場規模拡大ができるのではないかと考えます。
近年では、宇宙産業の実装に向けた取り組みがニュースで大々的に取り上げられるようになりました。多くの人の目に入るようになったからこそ、宇宙事業の「消費者」の目線から、持続的な技術・需要の地盤を固めていくことで、さまざまな面で宇宙産業が活きてくるのではないかと考えています。
——日本の民間企業がこれから宇宙産業を発展していくために、求められることは何ですか?
鈴木:日本や民間企業がより宇宙産業を発展させていくためには他企業、もしくは他国とタッグを組むということだと思います。それぞれの専門分野、得意分野から多くの知見を得ることができて相互がwin-winの関係を作ることができれば発展させることができると考えています。
また宇宙開発を行っていなかった企業の知見などを応用して宇宙産業に昇華させるということも可能でしょう。こういったあたらしいつながりが宇宙産業の発展に求められるのではないでしょうか。
——政府系機関、及び伝統的な航空宇宙産業が進めてきた従来型の宇宙開発「オールドスペース」。それら以外の新興の民間企業が進める宇宙開発「ニュースペース」。技術の進歩が民間企業でも宇宙産業にチャレンジできる1つの大きな要因になったと考えます。
もしもAI・ブロックチェーンといった、次世代のテクノロジーと宇宙開発が掛け合わさる未来があるとしたら、どのようなことを期待しますか?
和田:宇宙関連事業は、今が黎明期でもあることから次世代テクノロジーととても相性が良い分野であると考えています。たとえばWeb3.0の業界でいえば、「分散型科学(DeSci)」といわれるエコシステム構築が話題となっています。
いわゆる「研究・技術の情報共有」や「資金調達」の手段としての活用することで、政府や大企業のリソースに偏らない民間での宇宙開発を加速させていくことが可能になります。
また他業界とのかけあわせによる、これまでとは違った観点からのユースケース展開や、VR・遠隔技術などの発展途上の技術と組み合わせることで、テクノロジー相互の課題解決やあたらしい需要を開拓することができると考え、とてもわくわくしています。
今後もさまざまなアプローチを仕かけていく

——最後にこれから挑戦していきたいことをお訊かせください。
鈴木:これから挑戦したいことはモーターケースの材質の変更です。自分はエンジンの開発分野を担当してきました。また現在はアルミのモーターケースを使用して燃焼試験を行っています。
しかし、アルミでは重量もあり耐久性も低いため、新モーターケースが必要です。そこで、研究室の大学院生とCFRPのモーターケースの開発を一緒に進めてきました。大学院生はいつまでも自分を導いてくれるわけではないので、自分が引き継いで開発を行っていきたいと考えています。
和田:私個人としては、宇宙事業を「地上から」支えることができればと考えています。まずは「多くの人に身近に感じてもらうこと」、あわせて「業界に関わらずビジネスの一つとして展開していくこと」を目標に、さまざまなアプローチを仕かけていきたいです。
また宇宙ロケット部として、昨年に引き続き今年度もクラウドファンディングを行う予定です。Twitter等SNSでも随時情報をアップしていきます。少額からの参加も可能ですので、ぜひご支援いただければと思います!
Profile

◉鈴木 悠介│スズキユウスケ
神奈川大学工学部機械工学科3年、神奈川大学宇宙ロケット部部長

◉和田 聡一郎│ワダソウイチロウ
神奈川大学経済学部経済学科4年、神奈川大学宇宙ロケット部広報、神奈川大学web3研究会共同代表。
◉神奈川大学
神奈川県横浜市に2つキャンパス(文・理11学部)を構える総合大学。2023年4月には理工系学部の再編を行うなど、世界水準の研究・教育環境の実現に向け取り組む。神奈川大学宇宙ロケット部は、「超小型衛星を安全・安価に打ち上げる超小型ロケットの開発」を目的としたサークルで、同学宇宙構造研究室(高野研究室)と合同で活動。ロケット制作から打ち上げまでの大体を独自で開発し、2021年にはハイブリッドロケット到達高度国内最高記録(10.1km)を樹立。

