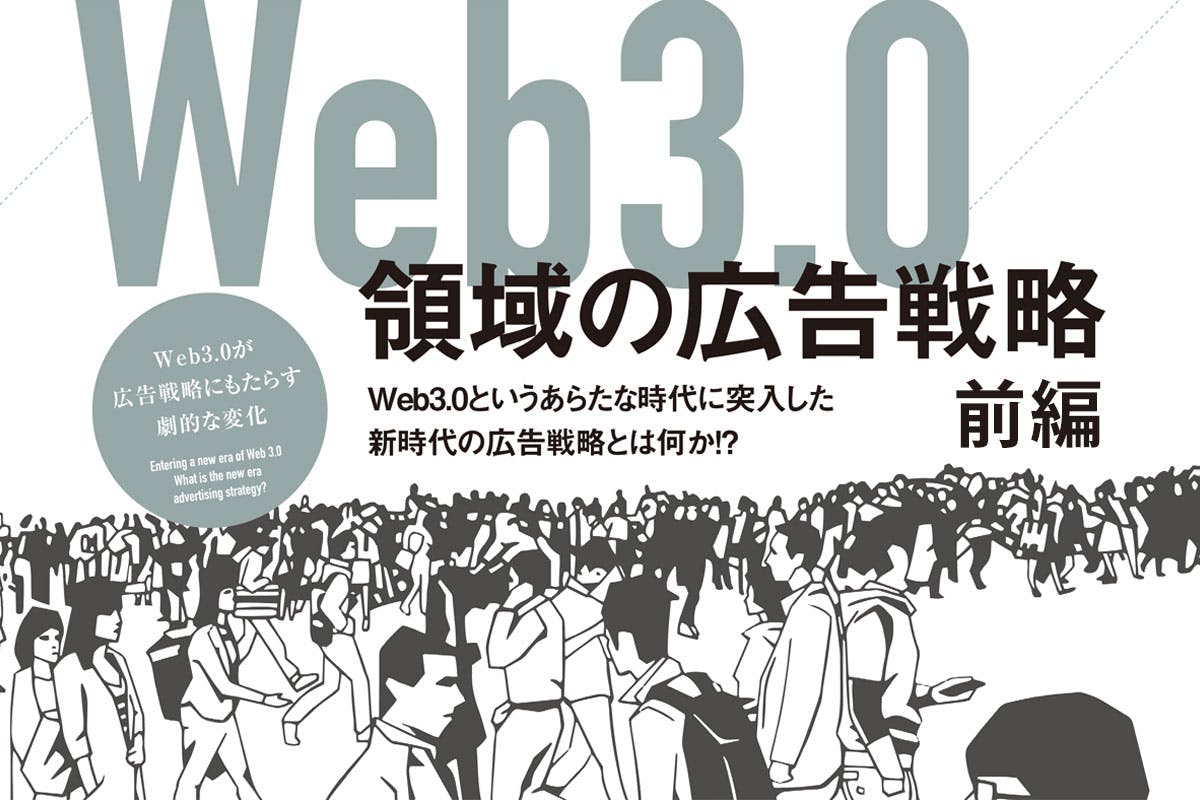
Web3.0領域の広告戦略 あらたな時代に突入した新時代の広告戦略とは?
Web3.0が広告戦略にもたらす劇的な変化
大手広告代理店の電通が毎年プレスリリースしている総広告費及び媒体別、業種別の広告費を推定した「日本の広告費」の2022年版によると、2022年の日本の総広告費は前年比104.4%の7兆1,021億円で、初めて7兆円を突破した2007年以来、過去最大となった。
そして、2023年のインターネット広告媒体費は引き続き順調に推移し、前年比112.5%の2兆7,908億円まで拡大すると予測されているが、さらにWeb3.0の登場で広告戦略は劇的に変化する。
Web1.0 「支払いに関する機能がなかった時代」
「支払い」に関する機能がなかったため、インターネットユーザーはオンラインでの情報公開に対して直接支払いを受けることができなかった。そのため、パブリッシャー・広告主・小売業者といったプレイヤーだけがさまざまな方法で収益化を試みるようになった。
Web2.0 「クローズドなプラットフォームの時代」
ブログ、SNS、ソーシャルブックマーク、RSSなどが登場。「情報をオープンにし、広告モデルでそれを 収益化する」という目標を立てたものの、大手プラットフォームの登場により結果的に、「クローズドなプラットフォームの時代」になってしまった。
Web2.0時代には1人のユーザーを中心に趣味や嗜好、興味・関心、主義が共通項としてつながり、そういった関係性が広告や物販、マーケティングなどにダイレクトに結びつくとする「インタレストグラフ」や、TwitterやFacebook等といったSNSにおける人間の相関関係がマーケティングなどに結びつくとする「ソーシャルグラフ」、そしてインタレストグラフとソーシャルグラフのハイブリッドを目指すとするのが、いわゆるWeb2.0時代のマーケティングの基本概念であり、各企業はそれに基づいた広告戦略を施策していた。
Web 2.0時代の広告は「ロングテール型」「集合地型」「リスティング型」「CGM型」 の4つの分野にわけられていた。
ロングテール型とは、個人のサイトやブログなどに広告を配信し、トラフィックをまとめて広告費を抑えるもので、アフィリエイトやアドセンスに代表されるコンテンツ連動型広告がある。
集合地型とは、SNSやブログなどで広告主にとって口コミ価値の高い広告をシェアして掲載料を取っていたもの。
リスティング型というのは、Yahoo!やGoogleなど検索エンジンでキーワード検索した際に、そのワードに連動して表示される検索連動型広告と検索結果の画面以外にも出せるディスプレイ広告の総称だ。
CGM型とは「Consumer Generated Media」の略で、主に口コミサイトやSNS、ブログ、掲示板(BBS)などに一般ユーザーが書き込むことでコンテンツが生成されていくメディアの総称である。
これらWeb2.0時代の広告手法はWeb3.0時代には通用しなくなるといわれている。
Web2.0時代には、Google、Apple、Facebook、Amazonといった企業が消費者に関するさまざまなデータを保有し、マーケティング活動に利用していた。
広告主も結局はプラットフォームの役割を果たしていたこれら企業を介して広告戦略を施策していたため、対費用効果でみて100%広告の恩恵を受けていたかというと、そうではない。当然、広告主もプラットフォームの役割を果たしている企業に広告費を支払っているからだ。
しかし、ブロックチェーンを基盤とした分散型のインターネットが普及すれば、データの所有権は個人に移行するため、これまでのマーケティング手法は通用しなくなる。
Web3.0の登場
「マーケティングや広告の概念も変化する」
マーケティングの概念が変われば当然、広告戦略も変わってくる。たとえば、 Web3.0の世界では広告代理店の役割も 変化していく可能性がある。先述した通り、 データの所有権が個人になるということは広告主も個人になるからだ。
現時点ではWeb3.0黎明期と呼べる時期なので、あくまで観測気球的な推測に過ぎない。トレンドワードのようにインターネット上に「Web3.0」というワードが躍り、プラスなイメージで語られることが多いが、当然、あらたな概念、時代の変革期においては、システムの変化に伴うトラブルもつきものだ。
有識者の間では、Web3.0時代の懸念すべきトラブルとして、悪意のある個人の力が強くなるであったり、ブラック・ハッカーが活発的になるとか、データ流出の際に歯止めが利かなくなるなどといった懸念が唱 えられている。
しかし、こうした懸念もあくまでいくつかある未来予測に過ぎない。起こるともいえないし、起きないともいえない。いざ実際に本格的なWeb3.0時代になった時、予想していなかった恩恵やトラブルがあるかもしれない。
Web3.0時代にWeb2.0時代の広告手法が通用しなくなるとしたら、どのようなマー ケティング概念や広告戦略になるのだろうか。
有識者によると、Web3.0時代は所有しているNFTトークンをユーザーごとに分析することで、そのユーザーの趣味嗜好を特定し、マーケティングなどに結び付くとする「トークングラフ」がマーケティングの基 本概念になるといわれている。では、トークングラフとは何なのか解説していこう。
注目の「トークングラフ」 とはなにか?
Web3.0時代は所有しているNFTトークンをユーザーごとに分析することで、 そのユーザーの趣味嗜好を特定し、マーケティングなどに結び付くとする 「トークングラフ」がマーケティングの基本概念になるといわれている。
ここまではブロックチェーンを基盤とした分散型のインターネットが普及すれば、 データの所有権は個人に移行するため、 Web2.0時代のマーケティング手法は通用しなくなるということと、この課題を解決するカギとなるのが「トークングラフ」であることを解説した。
トークングラフとは、ブロックチェーン上の公開情報からユーザーが所有するトー クン(NFTや暗号資産の総称)を参照することで保有者の趣味・嗜好を推測、親和性の高いNFTの配布や企業の製品・サービスの訴求を行い、マーケティングを強化できるというものである。

こうした「トークングラフ」をWeb3.0のマーケティング手法のひとつとして提唱しているのが、NFTの配信技術に強みを持つSUSHI TOP MARKETING株式会社の代表・徳永大輔氏である。
さらに同氏は『まず無料ノベルティのような形でNFTを配布したのち、ユーザーと継続的にコミュニケーションを取りながらマーケティングを行う手法が、Web3.0の時代では鍵を握る』 と指摘している。
同氏が提唱する「トークングラフマーケティング」とは、『トークングラフはWeb2.0のインタレストグラフとソーシャルグラフに取って代わるものではなく、そこに「追加」されるあたらしいマーケティング概念』という前提のもとに、『Web3.0上でその人が所有するトークンの情報、「トークングラフ」をもとにその人の属性や趣味嗜好を推し量り、NFTを送るマーケティング手法』のことであるとしている。
たとえば、あるウォレットのなかにVRに関するNFTが複数入っているとすると、そのユーザーの自宅にはVRのヘッドマウントディスプレイがあるという予測が立つ。 VR関連サービスを展開する企業は、そういうウォレットを選んで広告としてのNFTを送ることができる。
これが「トークングラフマーケティング」である。
では、具体的にWeb2.0のインタレストグラフ及びソーシャルグラフとWeb3.0のトークングラフとの違いは何だろうか。
SNSなどの利用から個人の属性を推し量るソーシャルグラフとブラウザなどの検索履歴によって趣味嗜好を推し量るインタレストグラフ。どちらもプラットフォームの役割を果たしている企業所有のデジタルデータに紐づいたマーケティングであり、 企業側から一方的にマーケティングされているというのがこれまでであった。
これに対して、トークングラフは個人が所有するデジタルデータに紐付いたマーケティングであり、所有するNFTを主体的に選択できるという点で、従来よりもユー ザーの意思を尊重したマーケティングである。
つまり、これまでの「誰がどんな趣味趣向をしているか」ではなく、「個人がどんなデジタルデータを所有しているか」という切り口でマーケティングを行うというのが大きな違いだといえるだろう。

以上が、トークングラフ、もしくはトークングラフマーケティングについての主な概要だ。では、広告主やユーザーにとって、このトークングラフマーケティングはどのような恩恵があるのだろうか。
まず、広告主はトークングラフマーケティングによって、「提供されるデータの確実性」を担保されることになる。これはNFTの持つ「替えの効かない唯一無二」「コピーや改ざんがされにくい」という性質に加え、「NFTデータの所有」という事実があるためだ。これにより、確実性を持ってターゲットを定め、分析する事ができるようになるのだ。
一方で、ユーザー側にとっては、「プライバシーの保護」が担保されることになる。 ターゲティングされるのは「対象NFTの所有者」であり、個人そのものではないからである。
以上のことを踏まえて広告業界に目を向けた場合、広告業界においても「どんなNFTを所有しているか」というトークングラフを用いたターゲットの選定と分析をしていくことになるため、これまでの年齢や性別でのターゲティングというのが難しくなるのではないだろうか。
また、検索広告のような「これから購入しようと考えている」ユーザーや「今リアルタイムで興味を持っ ている」ユーザーのターゲティングについても同じようにハードルが高くなることが予想されるだろう。

NFTとメタバースで広告業界はどう変わる?
メタバースやNFTの浸透が急速に拡大した場合、これら2つのあたらしい技術は広告業界に古くからある明確な3つの課題(手続きが煩雑、個人で広告枠を容易に買えない、グローバル性が乏しい)を解消できるのだろうか。
2021年末にFacebookが社名をMetaへ変更したことをきっかけにメタバースは世界的に注目を集めている。すでに国内外の幅広い業界の企業が相次いで参入を発表しており、メタバースの活用は幅広い業界・領域で進んでいくと考えられる。
そのなかでも特に大きなインパクトを持つと考えられるのが、広告・マーケティング領域での活用である。一方でメタバースなどのバーチャルな空間での利用が話題の中心になっているのがNFTである。
では、NFTとメタバースで広告業界はどう変わっていくのだろうか。

まず広告業界でのメタバース活用に注目が集まる理由として、現在はVRゲームを中心に利用が拡大しているメタバースだが、SNSやコマース、各種イベントなどさまざまな活動がメタバース上にシフトしていくと考えられている。
広告ビジネスは各時代の人々の視線が集まる領域を中心に発展してきたといわれており、テレビ→インターネット(Webサイト、SNS)の次の領域として想定されているのがメタバースというわけである。
また、広告・マーケティング活動をWebやSNSで行う場合とメタバース上で行う場合の大きな違いは、ユーザーに対してブランドが3次元の空間上でインタラクションを交えた体験を設計できることだ。
従来は各ブランドがリアルで開催していたイベントや、リアルでは実現の難しいゲーミフィケーションを交えた体験設計などを通じて、ブランドの世界観を体験してもらうこともメタバースでは可能となった。
さらに広告の費用対効果を決める要素としてユーザーデータの活用がある。ユーザーデータの活用が大きく進んだことによりインターネット広告の市場は急拡大を続け、テレビ・新聞広告の市場は縮小を続けている。
メタバースが人々の生活に浸透した場合、Web/SNS広告に比べて、より多くのユーザーデータを獲得できる可能性も考えられ、これらのデータを活用することで、従来のWeb/SNS広告に比べROIの高い広告を提供できる可能性もある。
広告業界におけるこうしたメタバースに対する期待と共に古くからの明確な課題点(手続きが煩雑、個人で広告枠を容易に買えない、グローバル性が乏しい)を解消する手段として期待されているのがNFTである。広告の権利売買にNFTを導入することで取引が簡易化され、透明性やスピードが向上するからだ。
従来はメディアと広告主が広告代理店を介して行っていたものが、NFTの導入でP2Pでのやり取りとなり、取引が簡易化されるほか、広告代理店が不要となるため、コストダウンにもなる。
また、もし権利化されたNFTがマーケットプレイスで販売されている場合は、ウォレットを持ってさえいれば、個人でも購入することができるのだ。さらにNFT導入で海外からでも日本の広告枠を買い取ることができる。
このように、このままメタバースやNFTの浸透が急速に拡大した場合、広告業界における長年の課題が解消されると共に、広告代理店の存在意義など、広告業界の構造改革的な変動が起こる可能性を秘めているのである。


インターネット広告に関する2023年6つのトレンド
Web3.0時代に突入する広告業界と期待される新技術。前年比112.5%の2兆7,908億円まで拡大すると予測されているインターネット広告。広告業界の構造改革的な変動が起こる可能性を秘めている過渡期の今、注目すべき6つのトレンドを紹介していく。
trend.1
インターネット広告は安定して伸長を続ける
▶大手広告代理店の電通が毎年プレスリリースを出している総広告費及び媒体別、業種別の広告費を推定した「日本の広告費」の2022年版によると、インターネット広告費は社会のデジタル化を背景に継続して高い増加率を保ち、前年比114.3%の3兆912億円となり、日本の総広告費全体の43.5%を占めているとしている。
また、2023年のインターネット広告媒体費は引き続き順調に推移し、前年比112.5%の2兆7,908億円まで拡大すると予測している。
trend.2
動画広告がさらに伸長する
▶電通の「日本の広告費」の2022年版によると、2021年のビデオ(動画)広告費は5,128億円。2020年から132.8%もの伸びをみせている。今後もこの成長傾向はより強まると考えられ、動画広告市場は6,000億円を超えると予測されている。
動画広告が好調である大きな要因の1つが、YouTubeやTikTokに代表される動画共有系SNSだが、動画共有系SNSが浸透した原因はやはり、コロナ禍における「お家時間」の増加によるものとしている。
trend.3
インストリーム広告の成長が期待される
▶伸長著しい動画広告市場のなかでも、これから特に成長すると予測されているのはインストリーム広告(動画コンテンツの途中に表示される動画広告)だ。好調なインストリーム広告に影響を与えているのが、TikTok・YouTubeのショート・Instagramのリールに代表されるショートムービー投稿プラットフォームで、2023年には日本でも年代層を広げつつ、さらに人気を獲得していくと予想されている。
trend.4
ソーシャル広告は今後も安定して存在感を示す
▶2021年のソーシャル広告費は7,640億円(前年比134.3%)と2020年から大きく伸長し、インターネット広告媒体費の35.4%を占めるようになった。年々存在感を増すソーシャル広告だが、先述したYouTubeやTikTokのインストリーム広告の好調を受けて、今後も安定した成長をみせ、ますます高い需要を獲得することが予想される。
trend.5
テレビメディアデジタルが好調
▶安定した成長が続くインターネット広告費のなかでも、マスコミ四媒体由来のデジタル広告費は前年比132.1%(1,061億円)と高い成長を記録している。
そのなかでも前年比146.8%という高い伸びをみせているのがテレビメディアデジタルだ。テレビメディアデジタル好調の大きな要因は、巣ごもり需要における動画配信サービスの浸透だが、2015年にサービス提供を開始した「TVer(ティーバー)」も大きな役割を果たした。
trend.6
データ活用とプライバシー保護の両立が重要
▶個人情報保護の機運の高まりを受け、個人情報の取り扱いに関する法規制が各国・各地域で厳格化してきている。2018年5月にはGDPR(EU一般データ保護規則)が施行、2020年1月にはCCPA(カリフォルニア州消費者プライバシー法)の適用が開始された。日本でも2022年4月に改正個人情報保護法が施行されている。
2023年にネット広告の精度が「ガタ落ち」する理由
欧州や米国の一部でCookieを個人情報だと断定し、第三者への提供を禁止した法律(EU一般データ保護規則)が施行された。GoogleやAppleもその潮流に乗って3rd Party Cookieを禁止した今、インターネット広告を活用する企業は広告手段の変更の決断を迫られている。
3rd Party Cookieを使わない広告手段へ移行する決断が迫る
2023年を境にネット広告の精度が「ガタ落ち」するといわれている。これはGoogleが2023年にCookieの第三者提供を廃止すると発表したことに起因している。
Cookieとは、スマートフォンやパソコンでインターネットを閲覧するため利用するSafariやChromeといったWebブラウザに自動的に埋め込まれる情報で、Webサイトで検索、閲覧、購買といった操作がユーザーの知らないところで個人(ブラウザのID)と紐付けられ、勝手に広告関連業者間で流通しているものだ。
「閲覧を続ける場合、Cookieの使用に同意したものといたします」というようなメッセージを閲覧したことがあるユーザーは少なくないはずだ。ユーザーの多くが訳もわからず「同意した」ことになっていることだろう。
Cookieの使用に同意すると、たとえば、「ネット通販で時計を買い物カゴに入れた20歳代の女性」といったような具体的な人物と行動履歴を追跡したデータを広告主は入手できるようになる。
ところが、欧州や米国の一部ではCookieを個人情報だと断定し、第三者への提供を禁止した法律(EU一般データ保護規則)が施行され、Cookieを規制する動きは、今、全世界に波及しようとしている。
先述したCookieに関するGoogleのプレス発表はこうした世界の潮流を受けてのものである。AppleはすでにSafariでの3rd Party Cookieによるサポートを2020年3月に廃止している。
広告を出稿する企業の多くは3rd Party Cookieを活用し、インターネット広告事業者などを通じて、インターネット上の行動履歴データを得ているが、3rd Party Cookieの利用が禁止となると、今までのように簡単にユーザーを判別できなくなる可能性が高い。それはつまり、ネット広告の精度の低下を意味してる。
その反対にSNS広告はもとより3rd Party Cookieに頼らず、アカウントユーザーをベースにした広告運営を行っているため、3rd Party Cookieの使用が禁止されたところでその影響は少なく、むしろネット広告の精度が落ちるのならば、従来ネット広告を出稿していた企業がSNS広告へと乗り換える可能性もあるため、SNS広告の費用は高騰する可能性すらあるだろう。
インターネット広告を活用する企業は3rd Party Cookieを使わないコンテキストマッチングといった広告手段へと移行する決断を迫られている。

