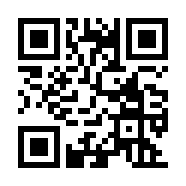被相続人が暗号資産をどこで管理していたかも、相続手続の難易度に大きく影響する。
国内の登録済み暗号資産交換業者(取引所)に預けていた場合、各社で相続対応のマニュアルが整備されつつあり、必要書類を提出すれば名義変更や出金手続きが可能なケースが多い。
たとえば死亡診断書や戸籍謄本、相続関係説明図などを所定のフォームで提出することで、取引所が遺産としての暗号資産を引き渡してくれる。
しかし、海外の無登録業者の口座やセルフカストディ型ウォレット(自分で秘密鍵を管理するウォレット)に保有していた場合、手続きは一気に困難になる。
外国の取引所では相続手続きの問い合わせ自体が言語や法律の違いでスムーズに進まないことも多く、場合によっては裁判所を通じた手続きを要求されることもある。
DeFi(分散型金融)上の資産やNFTなどについては、そもそも管理者が存在しないため、秘密鍵を承継できなければ資産そのものが消滅してしまう。
故人がメタマスク等のウォレットで管理していたDeFiトークンやNFTは、アクセス手段が無ければ移転は不可能だ。
暗号資産の相続は、技術・制度・リテラシーの齟齬が絡み合うあらたな“社会的盲点”であり、従来の財産にはない障壁が存在しているといえる。
デジタル資産の税務に詳しい、たまらん坂税理士法人 坂本新税理士も
「相続財産から暗号資産が漏れ、税務調査で指摘されれば修正申告を提出することになり、ペナルティとして加算税・延滞税まで賦課されます。生前から家族と暗号資産の情報共有をすることに加え、専門家に相談することが最大の備えです」と警鐘を鳴らす。
暗号資産の相続は、従来の相続にはない税務リスクと技術的問題が絡み合う複雑な領域である。
しかし同時に、誰にとっても無縁ではない現実の問題になりつつある。リスクを正しく認識し、今から備えを講じることが肝要だ。
具体的な対策としては、生前の情報整理と専門家との相談があげられる。
自身が保有する暗号資産の種類・数量・保管場所(取引所名やウォレットの詳細)をリスト化し、ログイン情報や秘密鍵の保管方法を信頼できる家族か専門家に伝えておくべきである。
必要に応じてマルチシグや信託の活用、先述の技術サービスの導入も検討しよう。
ただし技術ソリューションについては法的位置付けが不透明な部分も多いため、導入に際しては税理士や弁護士といった専門家に事前に相談すると安心だ。
税務面では、生前贈与や遺言信託など伝統的手法も組み合わせることで、課税額のコントロールや紛争予防が可能になる場合もある。
何より重要なのは、暗号資産の相続対策を「自分ごと」として捉え、早めに動くことである。
想定外の110%課税や資産消失に直面しないために、今この瞬間から備えを始めていただきたい。
暗号資産の相続は「消える資産」というリスクだけでなく、「デジタル資産への課税」という税務上のリスクも孕んでいる。日本国内の保有者はすでに500万人を超えるとされるが、相続税務を視野に入れた対策を講じる人はまだ少数だろう。
デジタル資産の相続を“自分ごと”として考え、相続人への情報共有と税務上のシミュレーションを行うことが、資産を守るための最初の一歩となるだろう。
文◉Noriaki Yagi
監修◉ 税理士 坂本 新 | Shin Sakamoto
たまらん坂税理士法人 代表社員・税理士
国税専門官採用試験に合格、東京国税局に入局。 都内の税務署及び東京国税局・徴収部・総務部・査察部に勤務後、法務省大臣官房租税訟務課出向、税務訴訟の国側訴訟代理人などに従事。
デジタル資産相続税務のご相談はこちらから▼
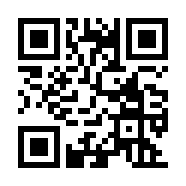 https://souzoku.shinsakamoto.com
https://souzoku.shinsakamoto.com