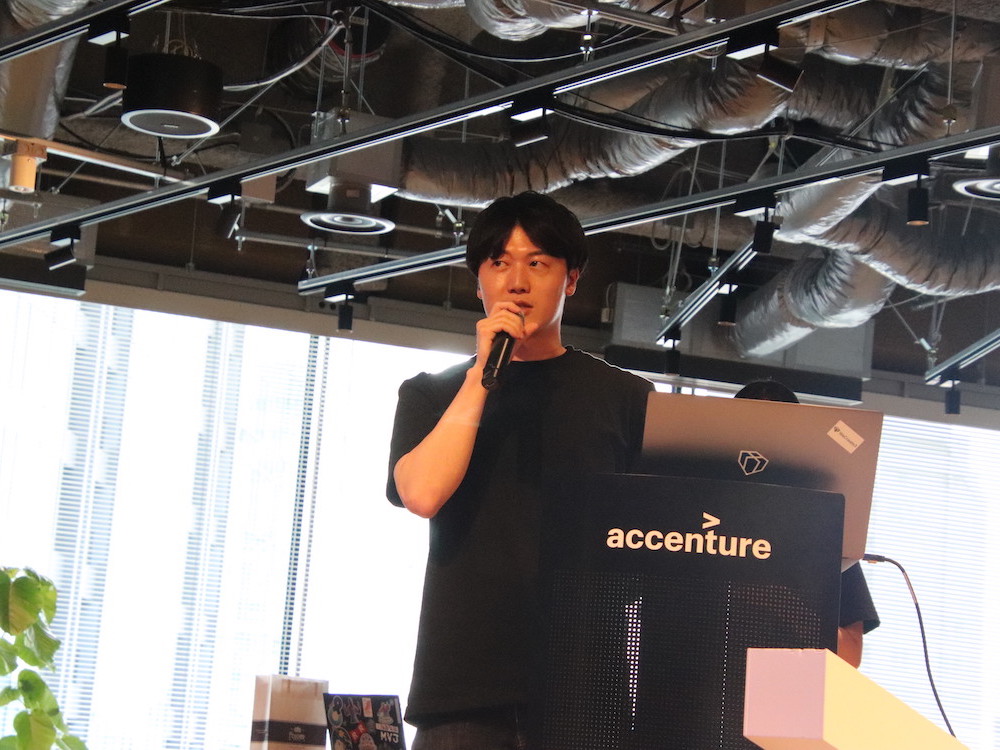▶︎左からとみね氏、雨弓氏、石濵氏、桐生氏
会話形式のセッションでは、Web3.0によるインセンティブについて話題となった。その代表例としてSTEPNがあげられ、今もなお多くのバリューを生み続ける背景にはユーザーインセンティブがあり、この仕組みを構築することがカギを握るとの声があった。
特にWeb3.0の参入障壁とされるウォレット等の普及について、石濵氏はわかりやすい例としてPayPayをあげた。
かつてほかの電子決済ツールがあれば事足りるとの認識が広まりつつあったなかで、PayPayはユーザーへの大規模なインセンティブを構築。数百億円規模の還元キャンペーンを実施したことで、瞬く間に世の中に浸透していった。
その過程でユーザーがPayPayを使うことに慣れていき、今もなお主要な電子決済ツールとして利用されていると解説する。Web3.0領域におけるウォレットやそのほかの参入障壁についても同様で、ユーザーへのインセンティブ設計が極めて重要であるとの考えを示した形だ。
こうした意見に桐生氏も自社のブロックチェーンゲームが浸透していった背景をもとに同意。東南アジアを中心に、「ユーザーへのインセンティブが重要な役割を果たした」と語った。
また、ユーザー側も最初は「お金が欲しくてコミュニティやっています。ゲームをやっています」という理由から始めるケースが多かったが、ゲームをプレイするうちに慣れていき、やることが当たり前になったと述べる。この当たり前になるという状況がユーザー数拡大の重要なポイントであったようだ。
Web3.0の普及に伴いどのようなことが起こり得るのかという点については、石濵氏の「法定通貨の使用が減る可能性がある」という言葉も印象的であった。
同氏は「Web3.0が浸透することで急激に使用頻度が減り、法定通貨だけではなく、イーサリアム(ETH)等の暗号資産なども並行して使っていかなければいけないといった考えが多くの人々の間で徐々に広がっていくのではないか」と主張した。
一方、雨弓氏は「Web3.0領域では学生にこそチャンスがある」と述べる。特に同氏の周辺では学生の価値は高く認識されているようだ。
理由は、「Web3.0ではまだ秩序が整っていないから」。雨弓氏は自身の経験も踏まえ、ブロックチェーンゲームをやっていればいつの間にか日本で最も詳しくなるといったことも起こり得ると指摘する。
背景には、大手を始め多くの企業がWeb3.0領域に関する知識、そしてノウハウ不足である現状がある。こうした状況も踏まえ、「学生はエンタメ、金融、ゲームと広がるWeb3.0の領域で好きなものが何かみつけられるはず」とし、「自分が好きなことをしながらかつ、企業から重宝される可能性があるのがWeb3.0の現状」と述べた。
学生であるという優位性を十分に有効活用してほしいとの言葉が印象的であった。